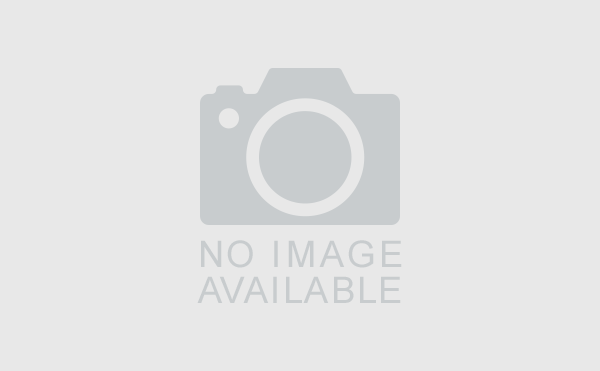高学年科学研究発表会
昨日、5・6年生の夏休みの課題であった「科学研究」の校内発表会がありました。一つの教室に集まり、代表児童(5年生2名・6年生3名)が発表しました。


どの発表も、子ども自身が日常の生活の中で、気になっていた事象に目を向け、「なぜ?」「どうして?」と思ったり「こうなったらいいなあ」「なんとかならないかなあ」と思ったりすることをきっかけにして、研究をスタートさせており、「時間と手間をかけながらも、根気よく実験を重ね、意欲的に研究に取り組んだな」ということがよくわかる発表でした。


発表を聞いていて特に感心したのが、研究の手順をしっかりと踏んでいることでした。「きっかけ」「予想」「実験」「観察」「結果」「考察」「まとめ」等、以前、理科センターの先生から教えていただいた「科学研究の進め方」の手順に従ってしっかりと研究進め、その様子を図や表を用いながらタブレットにまとめて発表していました。聞いていて、とても分かりやすく、「今年度もレベルの高い科学研究発表会だな」と感じました。
伊米ヶ崎小学校では、「科学研究」を夏休みの必須課題としています。毎年、3~6年生が必ず「一人1研究」に取り組んできました。(今年度は、夏休みの期間が短かったため、3・4年生は希望制)
科学研究の手法を身に付け、文書にまとめて発表するという取組は、子どもたちの「学びに向う力」や「思考力・判断力・表現力」を鍛えるうえで有効であると思っています。
これからも、この取組は伊米ヶ崎小学校の特色として続けてきたいと思います。